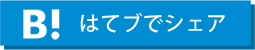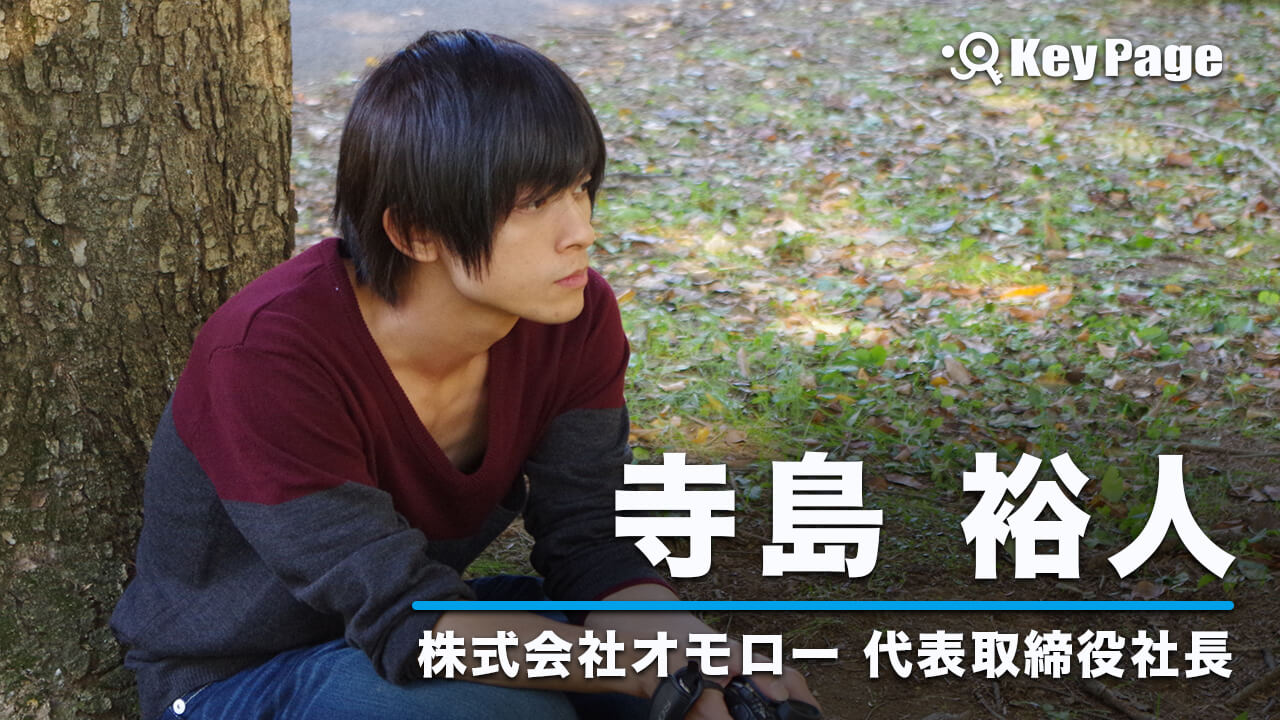岡田沙織 Episode1:「劣等感」という名の影が落ちた、その日から | KeyPage(キーページ):起業家の「人生を変えたキッカケ」を届けるメディア
» 岡田沙織 Episode1:「劣等感」という名の影が落ちた、その日から
“お誕生日、おめでとう”
家族みんなから温かく祝ってもらった「最後の誕生日」。わたしはまだ、4歳だった。
水商売をしている母は、家を空けることが多かった。父が仕事から帰ってくるとバタバタと玄関に走っていき、寂しさを埋めるように「おかえりー!」と抱きつく。
ところが、そんな日常は、ある夜を境にガラガラと音を立てて崩れた。
「ガッシャーン」
鏡が割れる音にびっくりし、目が覚める。
幼いわたしの瞳が捉えたのは、床に倒れている母とその横で立ちすくむ父の姿。 床に散らばった大量のガラスの残骸に、“ああ、きっとパパがママにやったんだな。” そう思った。 それからは突然の風が吹いたように、あっという間に家族は離れ離れに。 “ばいばい” わたしに手を振る母。 “どうしてわたしに手を振るの?” 両親の離婚はあまりに突然、わたしの日常に降りかかった。車に乗せ連れてこられたのは、祖父の家だった。 あまりのボロアパートに、息をのむ。いくつもの靴が散乱している狭い玄関。せんべい布団がひかれた四畳半一間の畳部屋。
ビルのある街を抜け、日常から遠ざかっていく電車。ばっと一瞬、眩しい光に包まれた景色に心を奪われた。 “うみ……海だ。” 海のある街で生まれたことを、思い出す。まだ、両親がいた頃の記憶。 ”死ぬなら、この海がいいなぁ。” その日を境に、学校へは行かず、海を見に電車に乗ることが増えた。 車窓から海を眺め、いつものように「死にたい」の4文字を心で呟く。 母は、わたしが学校に行っていないことがわかると、不機嫌な感情に任せてヒステリックに怒った。 「この金食い虫!!!!」 初めて母に反抗する私 “じゃあ、高校なんて辞めてやるよ!”
お金のかからない公立に行ったのに、なんでそんなこと言われないといけないの?!と心の中で叫んでいた。 反抗期を迎え、勢いで放った自分の言葉に後戻りできず、わたしはあっけなく「みんなと同じ」制服を脱ぐことになった。 高校を辞めたあとは、友達に誘われキャバクラやクラブで働いた。 それでも朝日が眩しい日は、制服を着た女子高生を羨ましく見つめた。片隅にはいつもある、「ふつう」の高校生活を送りたかった自分。
寂しい日常に負け、また薬に手を染めてしまう。 その日も、友達に部屋に招かれいつものようにシンナーを吸っていた。 だんだんと意識がもうろうとしてくる中、パッと目を開ける。なんと、男が、わたしの上に跨っていた。声を出して助けを呼ぼうとしても、身体も動かなければ、シンナーを吸っているせいで呂律もまわらない。 “や…めて……。” そのままレイプをされる自分が、悲しかった。 “ああ、わたし友達にはめられたんだ。こんな目に遭ってまで、何をやってるんだろう……。”
幼いわたしの瞳が捉えたのは、床に倒れている母とその横で立ちすくむ父の姿。 床に散らばった大量のガラスの残骸に、“ああ、きっとパパがママにやったんだな。” そう思った。 それからは突然の風が吹いたように、あっという間に家族は離れ離れに。 “ばいばい” わたしに手を振る母。 “どうしてわたしに手を振るの?” 両親の離婚はあまりに突然、わたしの日常に降りかかった。車に乗せ連れてこられたのは、祖父の家だった。 あまりのボロアパートに、息をのむ。いくつもの靴が散乱している狭い玄関。せんべい布団がひかれた四畳半一間の畳部屋。


ビルのある街を抜け、日常から遠ざかっていく電車。ばっと一瞬、眩しい光に包まれた景色に心を奪われた。 “うみ……海だ。” 海のある街で生まれたことを、思い出す。まだ、両親がいた頃の記憶。 ”死ぬなら、この海がいいなぁ。” その日を境に、学校へは行かず、海を見に電車に乗ることが増えた。 車窓から海を眺め、いつものように「死にたい」の4文字を心で呟く。 母は、わたしが学校に行っていないことがわかると、不機嫌な感情に任せてヒステリックに怒った。 「この金食い虫!!!!」 初めて母に反抗する私 “じゃあ、高校なんて辞めてやるよ!”
お金のかからない公立に行ったのに、なんでそんなこと言われないといけないの?!と心の中で叫んでいた。 反抗期を迎え、勢いで放った自分の言葉に後戻りできず、わたしはあっけなく「みんなと同じ」制服を脱ぐことになった。 高校を辞めたあとは、友達に誘われキャバクラやクラブで働いた。 それでも朝日が眩しい日は、制服を着た女子高生を羨ましく見つめた。片隅にはいつもある、「ふつう」の高校生活を送りたかった自分。

寂しい日常に負け、また薬に手を染めてしまう。 その日も、友達に部屋に招かれいつものようにシンナーを吸っていた。 だんだんと意識がもうろうとしてくる中、パッと目を開ける。なんと、男が、わたしの上に跨っていた。声を出して助けを呼ぼうとしても、身体も動かなければ、シンナーを吸っているせいで呂律もまわらない。 “や…めて……。” そのままレイプをされる自分が、悲しかった。 “ああ、わたし友達にはめられたんだ。こんな目に遭ってまで、何をやってるんだろう……。”

掲載日:2019年06月21日(金)
このエピソードがいいと思ったら...
岡田沙織のエピソード一覧

NPO法人若者メンタルサポート協会理事長、あすぷろ実行委員会理事
岡田沙織(おかだ さおり)
NPO法人を立ち上げ、生きることにもがき苦しむ多くの10代に寄り添い、あなたはあなたのままでいいと無償の愛を注ぐ岡田さん。薬物、DV、中絶、離婚、裏切り...幼少期から今日まで至る壮絶な過去は「宝物」と胸を張って語る彼女の生き様ときっかけを伺いました。