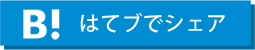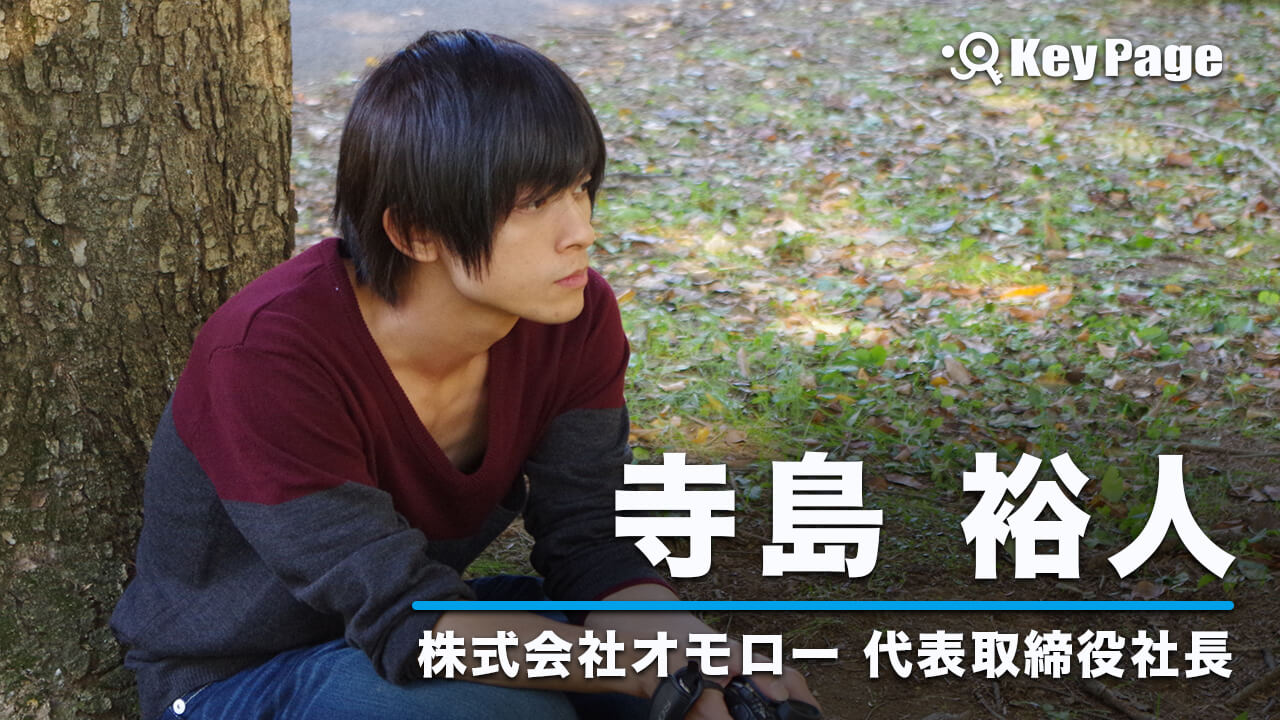小室友里 Episode2:能ある鷹が爪を磨かず隠し続けてきた、そんな学生時代。 | KeyPage(キーページ):起業家の「人生を変えたキッカケ」を届けるメディア
» 小室友里 Episode2:能ある鷹が爪を磨かず隠し続けてきた、そんな学生時代。

「小室さん、お疲れさま。ホントやりやすかったよ。ありがとう」
私ひとりに宛てたねぎらいの言葉。
小学校、中学校、と進むにつれ、クラスの委員長や学級担任、部活の顧問……そうした立場の人たちに、「小室がいてくれて助かった」としばしば言われるようになった。
自分で言うのもなんだが、成績が良い。運動神経も良い。容姿も端麗だ。
トップに立つにふさわしいポテンシャルを客観的に兼ね備えており、事実周りからもそのように見られていた。
けれども私は一度も組織の一番上に立つことがなかった。
一番上に立つということは、そこから転がり落ちる可能性を同時に引き受けるということ。そのうえで引き受けた責任感とはなんとも強く輝かしいものだが、わたしにはそんなご立派な責任感も覚悟もなかった。
ほめられたい。目立ちたい。みんなに憧れられたい。事実、私は憧れられている。
………けれども、転落の恐怖までは引き受けられない。
だから私は常に二番手のポジションを取った。トップを支える誰より優秀な、例えばクラスの副委員長、例えば書記。部活はプレイヤー兼マネージャーでありながら、県大会の常連。という不思議な……周到なポジショニングをしていた。
転落するのは怖い。けれどもほめられたい。目立ちたい。憧れられたい………もっと、もっと。
ブラウン管の向こうで笑顔を振りまくアイドル達。みんなに憧れられ、かわいがられ、キラキラ輝くそんな女の子。
「アイドルになりたい」
いつしか私の心にそんな願いが生まれ、エキストラのアルバイトを始めた。
トップに立つ恐怖は拭い去れぬまま、トップを勝ち取る努力もできぬまま、10代も後半になっていた私は芸能界に片足を突っ込んだのだった。
掲載日:2017年06月23日(金)
このエピソードがいいと思ったら...
小室友里のエピソード一覧

ラブヘルスカウンセラー
小室友里(こむろ ゆり)
AV女優として一世を風靡し、現在では男女の性やコミュニケーションについて執筆、講演活動をされる小室友里さん。語っていただいたその性の原体験は、意外なものでした……。