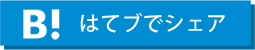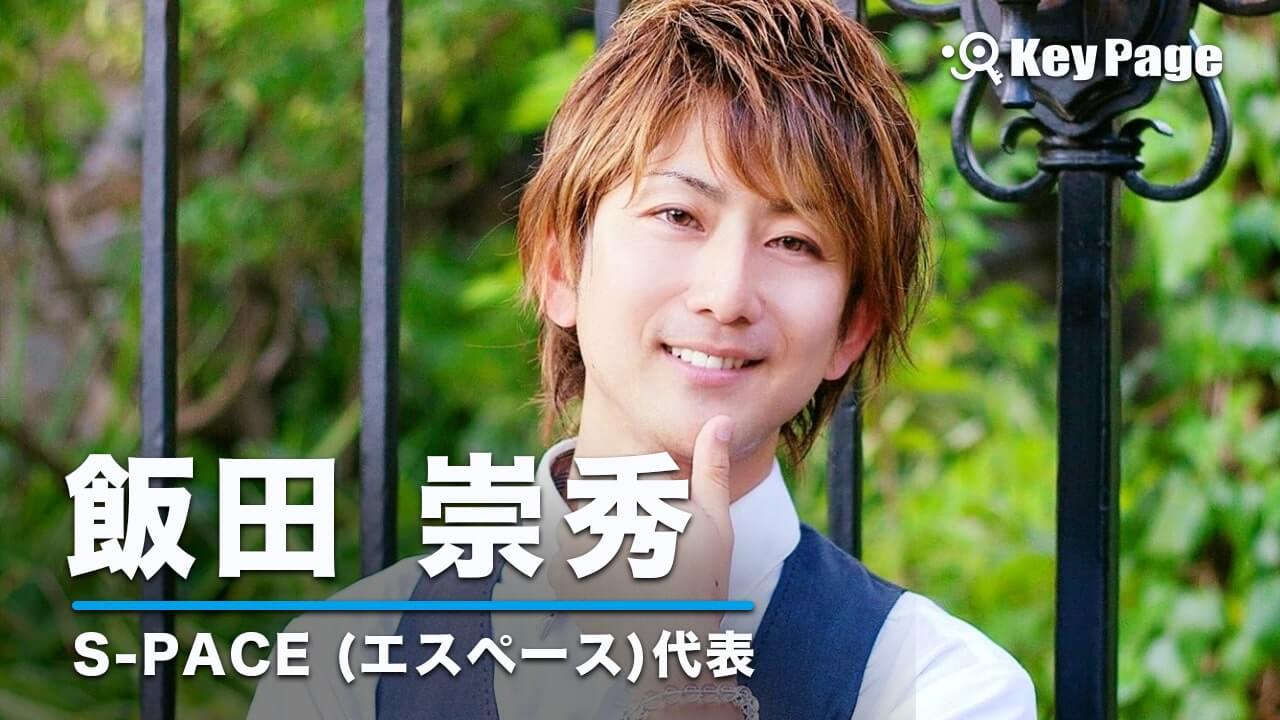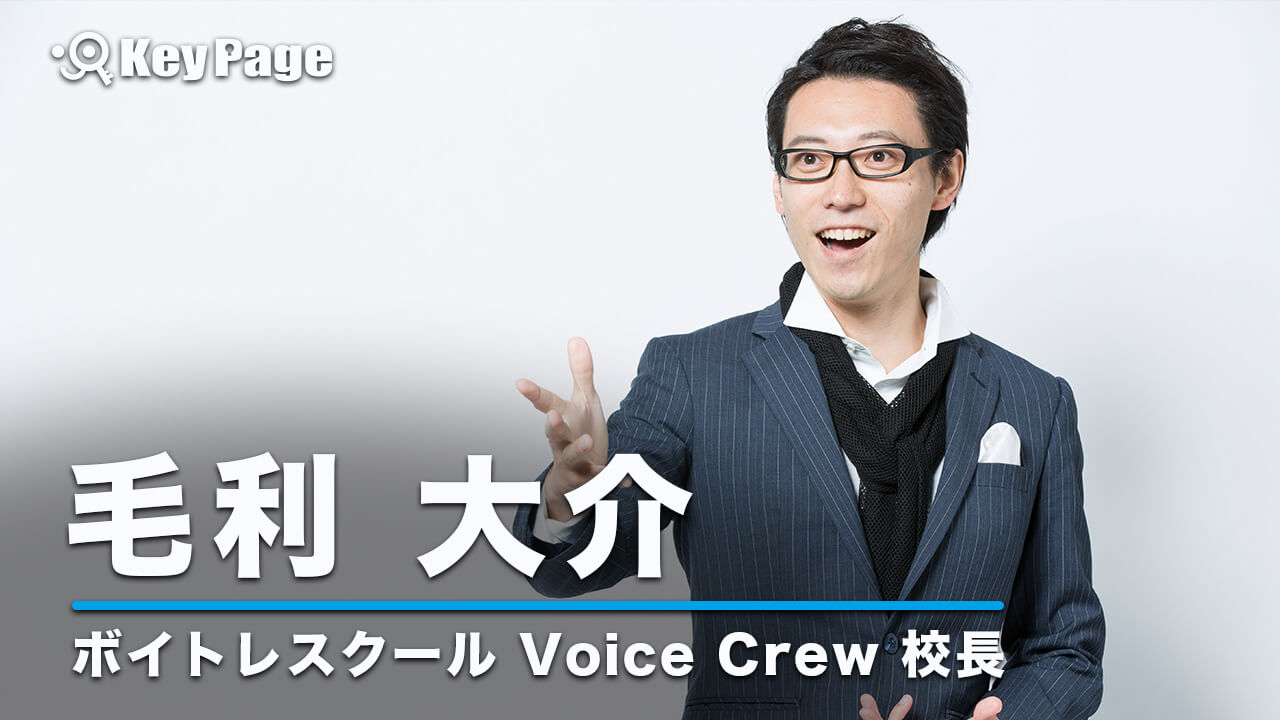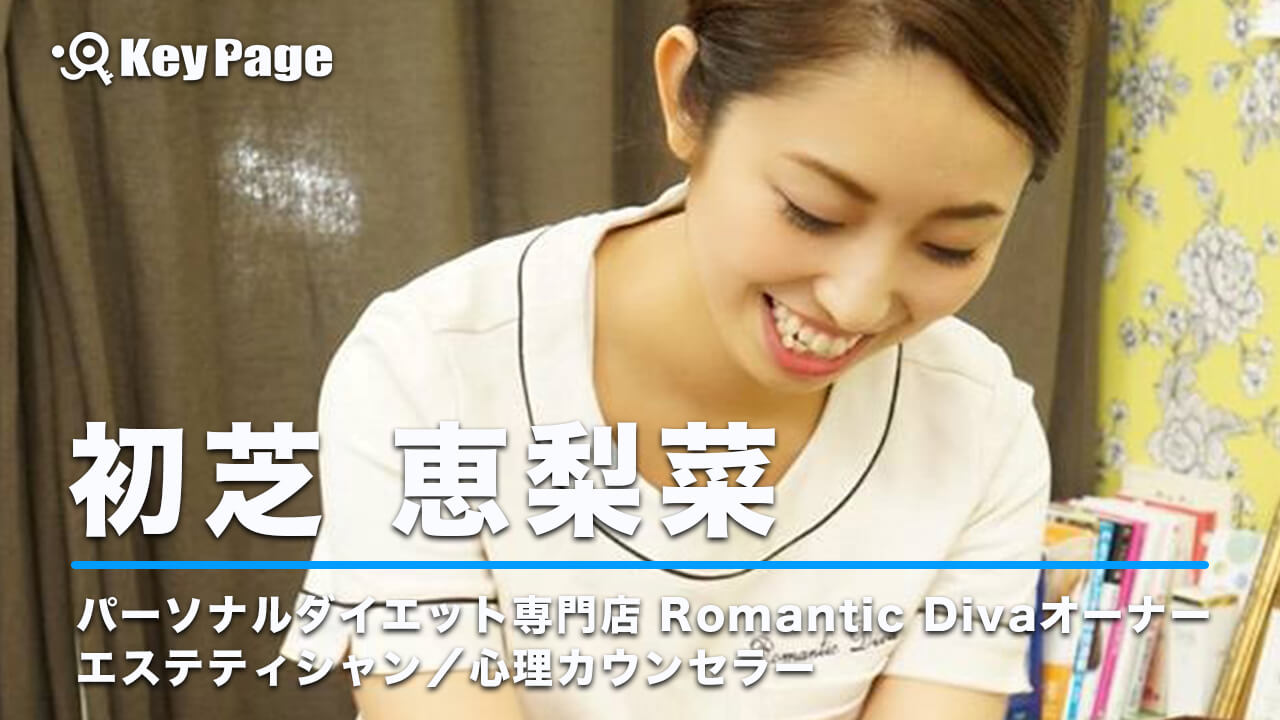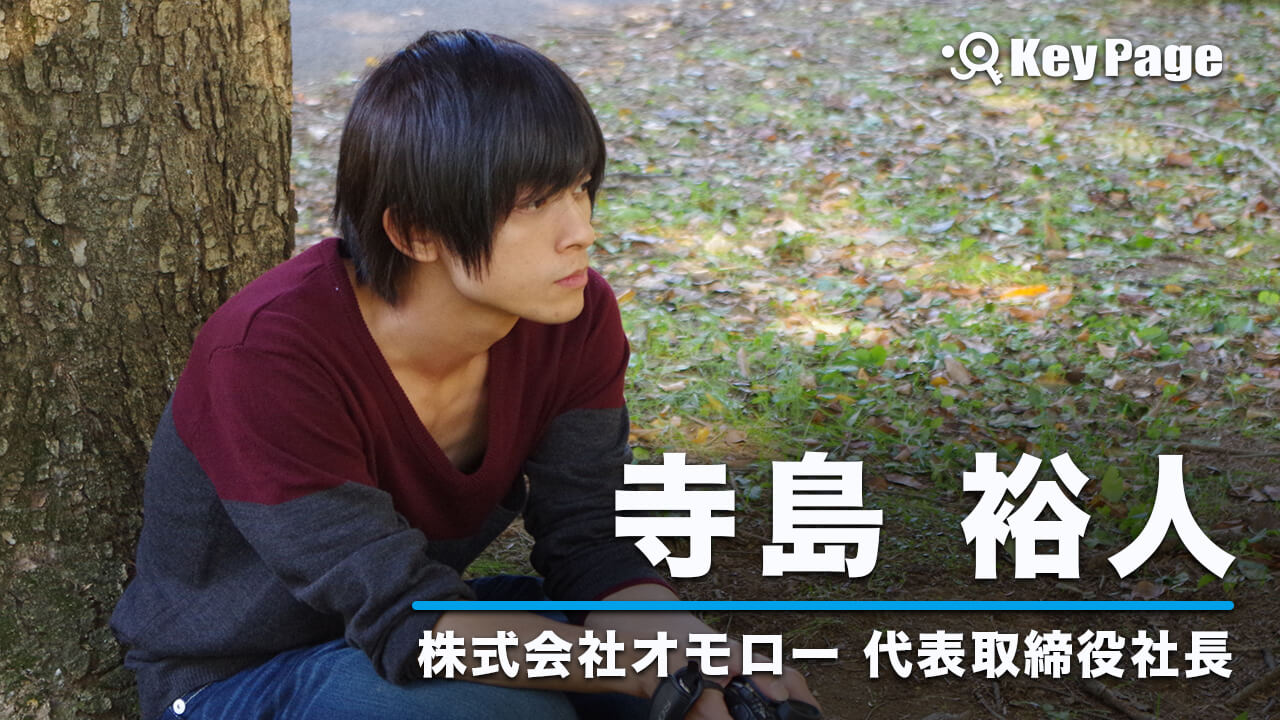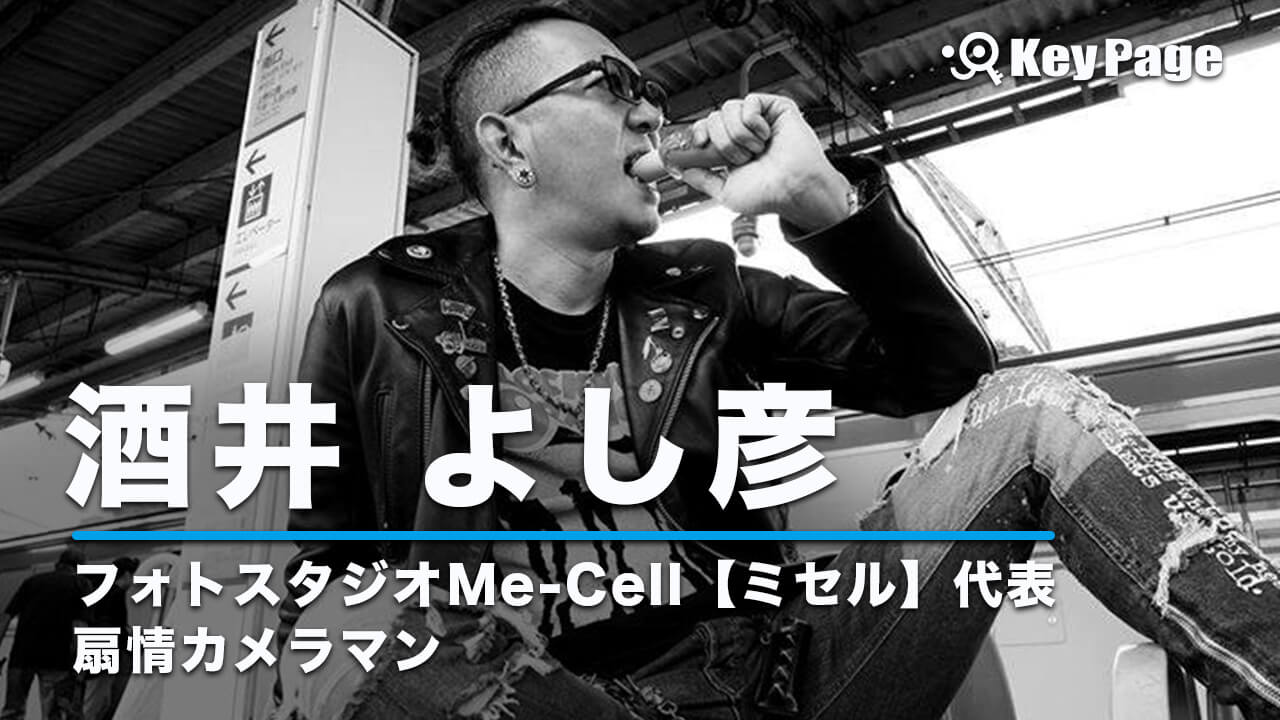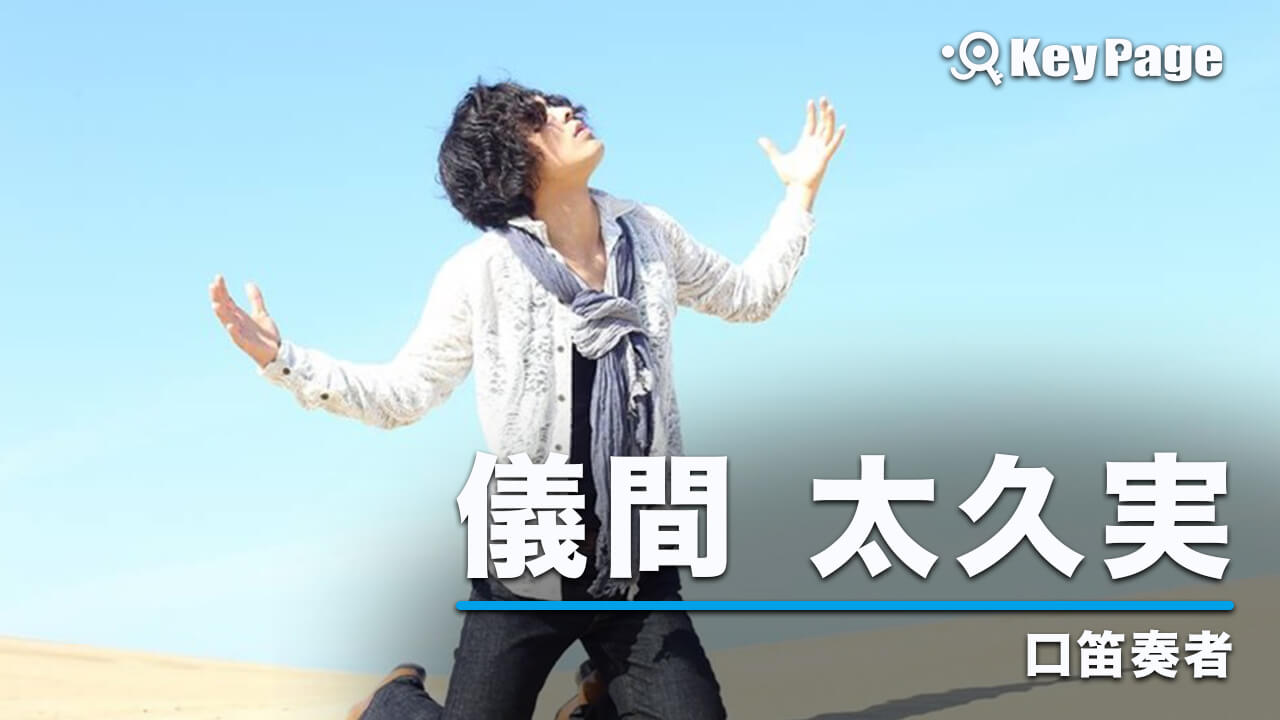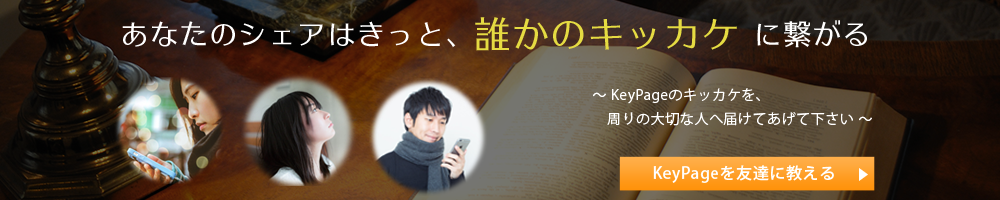日置祐輔 Episode2:インドの旅、そして見つけた自分の「在り方」 | KeyPage(キーページ):起業家の「人生を変えたキッカケ」を届けるメディア
» 日置祐輔 Episode2:インドの旅、そして見つけた自分の「在り方」
大学4年生になった僕は、社会人になる前に、どうしても行きたかった場所に出かけた。
親友と男2人で訪れたそこは、インド。2週間ほど滞在した中で、僕は価値観が大きく揺れる体験をたくさんした。
手を靴の中に入れて歩く人がいるので見ると、両足がない。手を差し出されたその手に、指がない、など。聞くところによると、自ら体の部位を切断して、「哀れな自分」になることで、物乞いをする方もいるということだった。五体満足が当たり前ではないその光景に、僕は言葉にならない衝撃を受けた。 その夜、僕たちは高級なホテルではなく、インド北東部の仏教の聖地、ブッダガヤという街にある、一泊200円ほどの安宿に泊まった。
ドアはなく、水道をひねると茶色い水が出る。そして当然、電気はない。朝、ヤモリが天井から落ちてきて、その気配で目覚める。それが朝の合図だった。日本の当たり前が、いかに当たり前でないかを身をもって感じた。 ノープランで旅を組んでいたので、時間に追われることもなく目を覚ましたあと、カビっぽいベッドの上で、2時間ほどぼーっとひび割れた天井を見つめていた。ふとその天井の隙間から一筋の太陽の光が入り込んできた。僕は何故か、その美しさにくぎ付けになってしまった。 そしてふとこう思った。 “あ、俺、あの太陽のようになりたい。” 僕の苗字は「日置」という。 “「日を置く」と書いて、日置…。” 生まれてから今まで、何も考えずに名乗っていたその名前の意味と、天井の隙間から見える太陽がリンクした瞬間だった。 人やモノには影がある。人が唯一影を作らない方法は、その人自身が光の源になること。だから、その人自身が輝ける、そのきっかけを提供できるような、誰かに「日」を「置」き届けられるような人間でありたい。
ふと思い浮かんだそれは、なんだか自分の使命のように感じられた。

手を靴の中に入れて歩く人がいるので見ると、両足がない。手を差し出されたその手に、指がない、など。聞くところによると、自ら体の部位を切断して、「哀れな自分」になることで、物乞いをする方もいるということだった。五体満足が当たり前ではないその光景に、僕は言葉にならない衝撃を受けた。 その夜、僕たちは高級なホテルではなく、インド北東部の仏教の聖地、ブッダガヤという街にある、一泊200円ほどの安宿に泊まった。
ドアはなく、水道をひねると茶色い水が出る。そして当然、電気はない。朝、ヤモリが天井から落ちてきて、その気配で目覚める。それが朝の合図だった。日本の当たり前が、いかに当たり前でないかを身をもって感じた。 ノープランで旅を組んでいたので、時間に追われることもなく目を覚ましたあと、カビっぽいベッドの上で、2時間ほどぼーっとひび割れた天井を見つめていた。ふとその天井の隙間から一筋の太陽の光が入り込んできた。僕は何故か、その美しさにくぎ付けになってしまった。 そしてふとこう思った。 “あ、俺、あの太陽のようになりたい。” 僕の苗字は「日置」という。 “「日を置く」と書いて、日置…。” 生まれてから今まで、何も考えずに名乗っていたその名前の意味と、天井の隙間から見える太陽がリンクした瞬間だった。 人やモノには影がある。人が唯一影を作らない方法は、その人自身が光の源になること。だから、その人自身が輝ける、そのきっかけを提供できるような、誰かに「日」を「置」き届けられるような人間でありたい。
ふと思い浮かんだそれは、なんだか自分の使命のように感じられた。

掲載日:2019年10月12日(土)
このエピソードがいいと思ったら...
日置祐輔のエピソード一覧

株式会社Sun’s代表取締役
日置祐輔(ひおき ゆうすけ)
株式会社Sun’s代表取締役。お金と時間と人を稼ぐをテーマにビジネスコミュニティを展開し、副業の学校や起業支援をしている日置祐輔さん。自信がなかった幼少期を経て、人の縁に恵まれながら今の自分になっていく、その心境の変化を追いました。